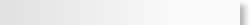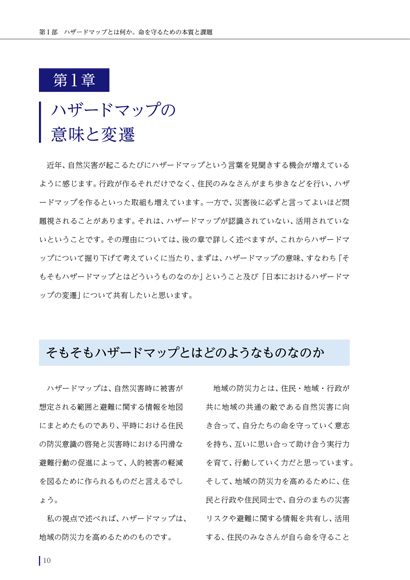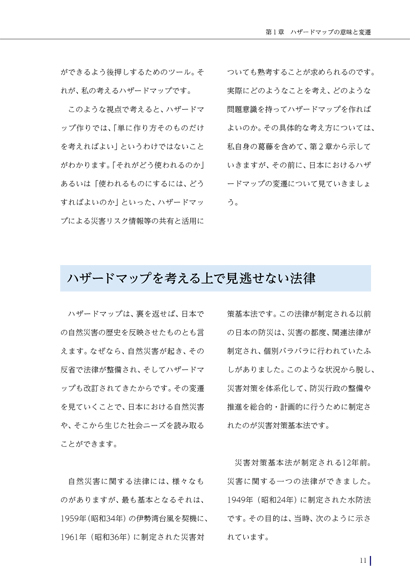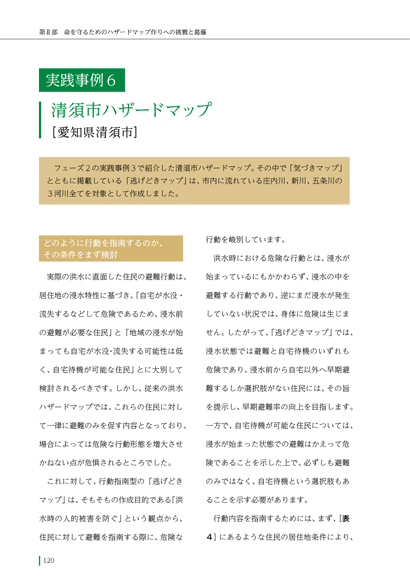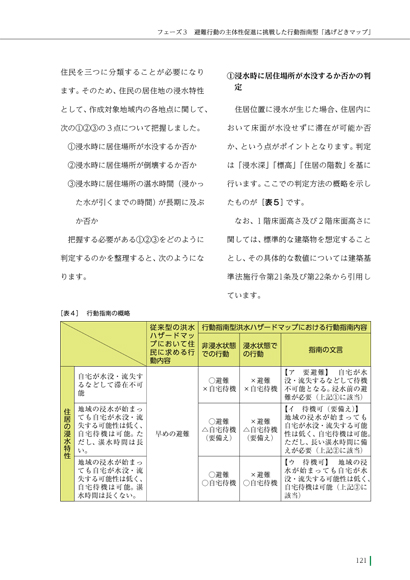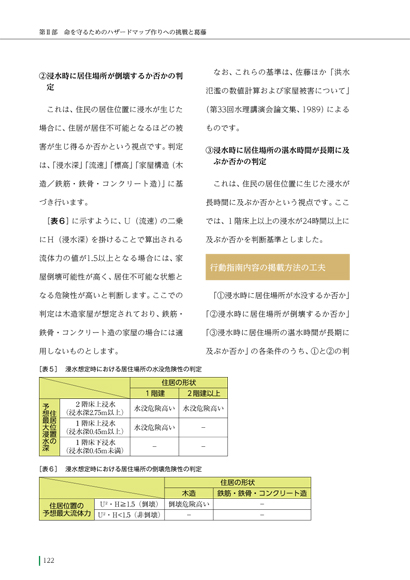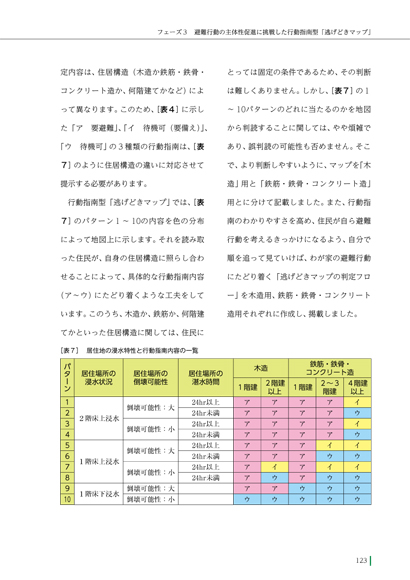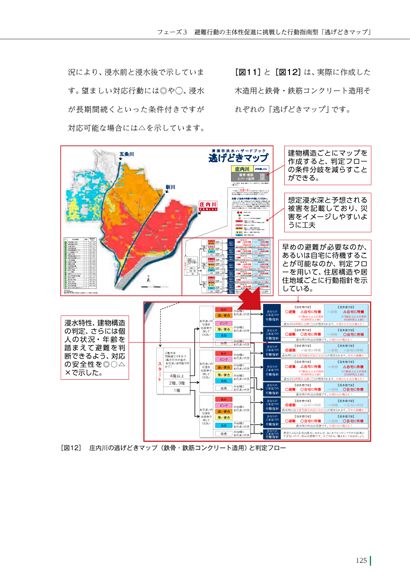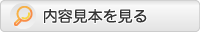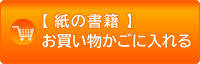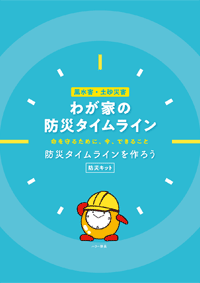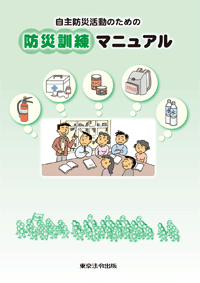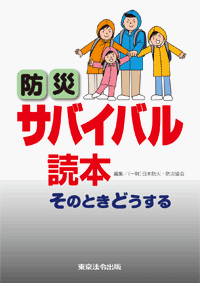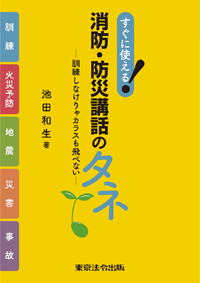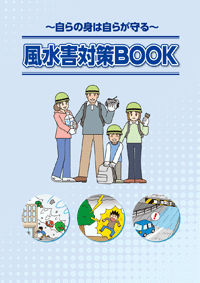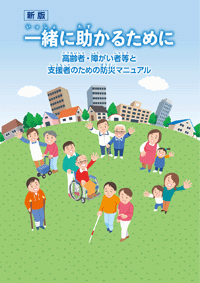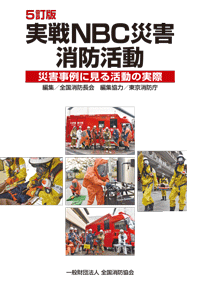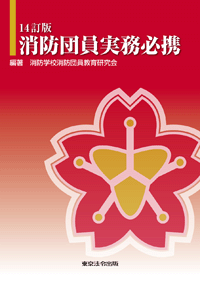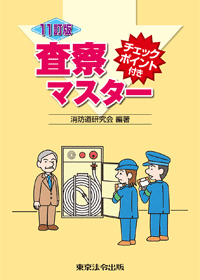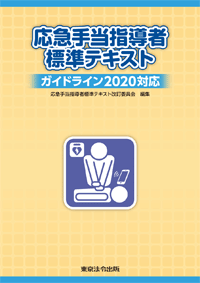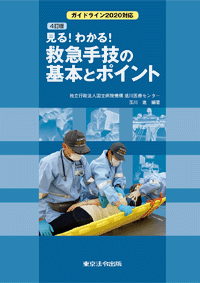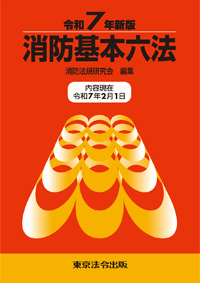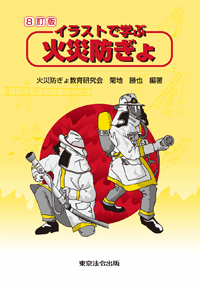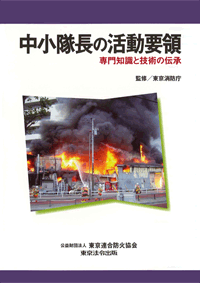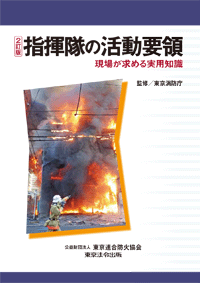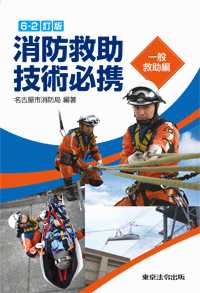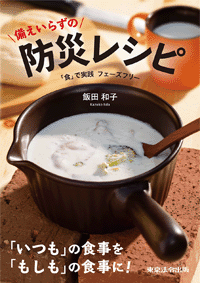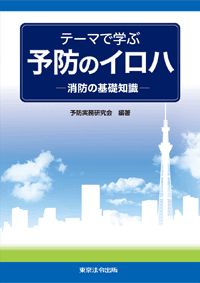ハザードマップで防災まちづくり
−命を守る防災への挑戦−

- 東京大学大学院情報学環特任教授 片田 敏孝 著

- A4判 184ページ

- 3,300 円(消費税込み)

- 3,000 円+税

- ISBN978-4-8090-2475-7
C3036 \3000E 
- 令和2年4月1日
本書の特長
- 「ハザードマップとは何か」
災害時の避難や避難情報を長年にわたり研究してきた防災研究の第一人者が、ハザードマップ作りを通じ、命を守るための本質と課題を徹底解説しています。
- 「どうしたらハザードマップを見てもらえるのか」「どうしたら危険性を正しく理解してもらえるのか」
数々の課題に応える工夫が反映されたハザードマップの実例(5分類12事例)を紹介。“わがまち”のハザードマップ作りのヒントが満載です!
はじめに(抜粋)
「災害があっても命を守り抜く」
1997年(平成9年)から防災研究者として活動をしてきた私の目的は何かと問われれば、一点の曇りもなく明確にそう答えます。命を守り抜く、すなわち自然災害で人が死なないために、防災研究者として何ができるのか、防災はどうあるべきなのかを考え、悩み、行動し、疑問にぶつかり、また考える。その積み重ねで防災現場と向き合ってきました。
自然災害で命を守り抜くために最も必要なこと、それは、被害に遭う前に避難することです。言われてみれば当たり前の話ですが、これがなかなか難しいのが現実です。
災害の本質は、誰にとっても予想もしないことが起こること。もっと正確に言えば、「誰にとっても予想もしたくないことが起こる」ことです。そして、予想もしたくないため、備えも怠りがちになります。なぜなら、備えという行動は、起こる事態を想定して取る行動だからです。避難が難しい理由もそこにあります。
避難することは難しい。「そうであっても、自然災害で命を落としてほしくない!」私が防災研究と活動を続ける理由は、やはりこの一点に尽きるのです。
1994年(平成6年)、河川洪水を対象に始まった日本のハザードマップは、20年以上の月日を経て、現在では、ほぼ全ての自然災害を対象に作成され、広く普及してきています。
地域それぞれでの防災活動がより重要になってきている中で、ハザードマップを作る必要に迫られながらも、どのように作ればよいのか、何を伝えていくべきなのかに迷い、悩んでいる現場担当者の方も多いのではないでしょうか。
そんなみなさんに心から伝えたいことは、「何のためにハザードマップを作るのか」ということに立ち返って考えてほしいということです。
「ハザードマップは、自然災害から自分たちの命を守り抜く地域防災力を高めるために作るもの」だと私は考えています。その視点で「自分のまちから自然災害の犠牲者を出すものか!」という気概を持ち、ハザードマップ作りと真摯に向き合い、その活用の仕方も含めて考えてほしいと願っています。
この本が、ハザードマップ作りや防災を考えるきっかけ、地域防災の一助になれば、こんなにうれしいことはありません。
令和2年1月
東京大学大学院情報学環特任教授
片田 敏孝
目次
- はじめに
- 第Ⅰ部 ハザードマップとは何か。命を守るための本質と課題
- 第1章 ハザードマップの意味と変遷
- そもそもハザードマップとはどのようなものなのか
- ハザードマップを考える上で見逃せない法律
- 水防法とハザードマップの変遷
- 努力目標として位置づけられたハザードマップ
- 義務化されたハザードマップの作成・周知
- 津波の追加とL2想定と住民目線でのハザードマップ
- 施設では防ぎきれないというスタンス
- 第2章 ハザードマップを作成・理解する上で心に留めておきたい前提
- 地球規模で警鐘を鳴らす荒ぶる自然
- 豪雨災害対策・これまでの弊害
- 災害過保護〜行政依存の住民意識〜
- 災害をめぐる住民と行政との関係
- アメリカとキューバに学ぶこれからの日本の防災
- 第3章 本質は、リスク・コミュニケーションツール
- 一方的なインフォメーションツールではない
- 犠牲者を出さないためのリスク・コミュニケーションツール
- 問われる行政の主体性
- 第4章 ハザードマップが効かない。最初にぶつかった現実
- 調査1 被災経験のあるまちでの全国に先駆けた洪水ハザードマップ検証
- 第5章 なぜ人は、避難しないのか。どうしてハザードマップは利用されないのか。
- 避難しないのではなく、避難できない人の特性、「正常化の偏見」と「認知的不協和」
- ハザードマップが利用されない背景
- 受け身の自助が情報を閉ざす
- 真の敵は自然災害ではない
- 第6章 リスク・コミュニケーションツールとしてのハザードマップの課題
- ①災害リスク情報を取得し、避難する住民の主体性を引き出す
- ②災害イメージの固定化、安全情報との誤解を回避する
- ③作って終わりではなく、作ってからが始まり! 使い方を考え、コミュニケーションツールとして活かす
- ④地域の特性を踏まえて災害リスク情報を提供する
- 第1章 ハザードマップの意味と変遷
- 第Ⅱ部 命を守るためのハザードマップ作りへの挑戦と葛藤
- フェーズ1 諦めたくなかった。災害イメージの固定化を崩し、情報取得の主体性を育むことに挑む。最初の挑戦!「概略表記型ハザードマップ」
- 実践事例1 岐南町洪水ハザードマップ
- 実践事例2 扶桑町水害対応ガイドブック
- フェーズ2 地域の特徴を表現することに注力した「気づきマップ」
- 実践事例3 清須市ハザードマップ
- 実践事例4 岡崎市水害対応ガイドブック
- 実践事例5 北九州市防災ガイドブック
- フェーズ3 避難行動の主体性促進に挑戦した行動指南型「逃げどきマップ」
- 実践事例6 清須市ハザードマップ
- 実践事例7 三条市豪雨災害対応ガイドブック
- フェーズ4 これからの避難に避けられない視点。広域避難とL2想定に挑戦したハザードマップ
- 実践事例8 戸田市ハザードマップ
- 実践事例9 新宮市津波ハザードマップ
- フェーズ5 避難できない人間の性を打ち破りたい!! 住民が作成に参画する、主体的な行動マップへの挑戦
- 実践事例10 桐生市土砂災害緊急避難地図
- 実践事例11 戸田市緊急避難場所マップ、まかせて会員・おねがい会員
- 実践事例12 北九州市みんな de Bousai まちづくり推進事業
- フェーズ1 諦めたくなかった。災害イメージの固定化を崩し、情報取得の主体性を育むことに挑む。最初の挑戦!「概略表記型ハザードマップ」
- おわりに
おすすめ商品