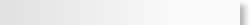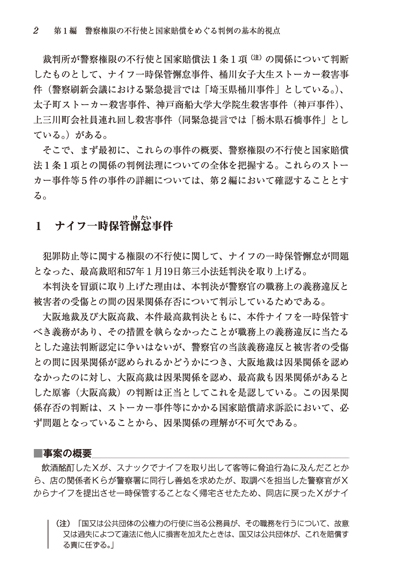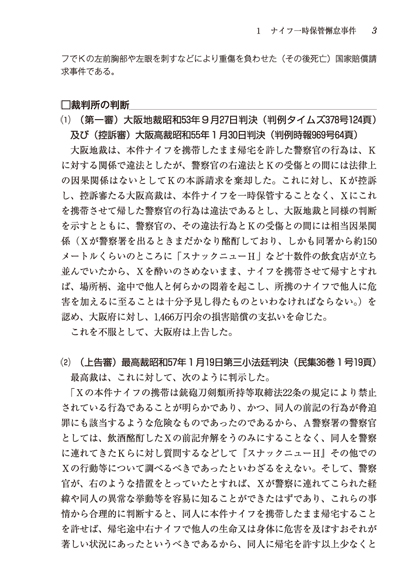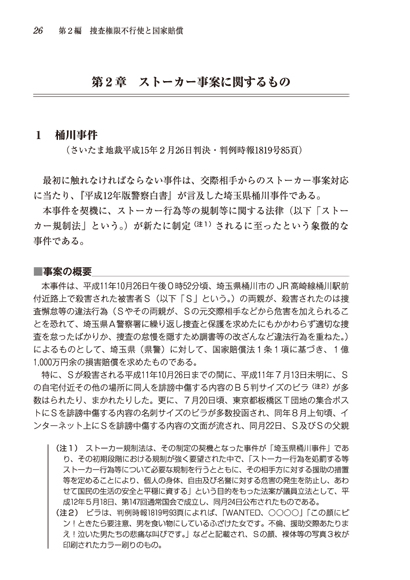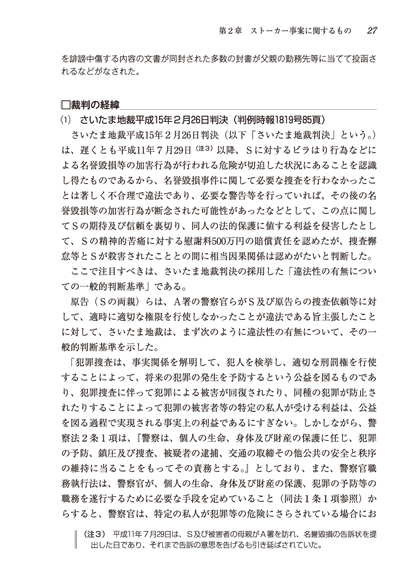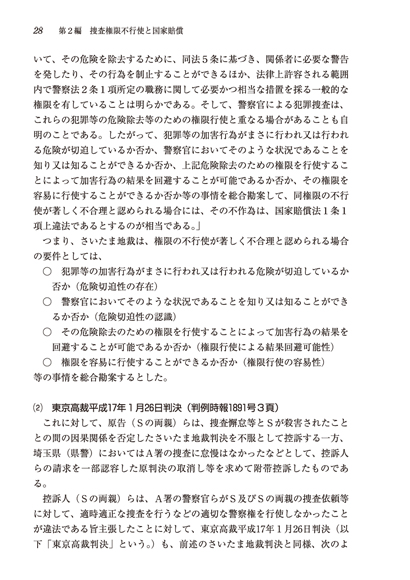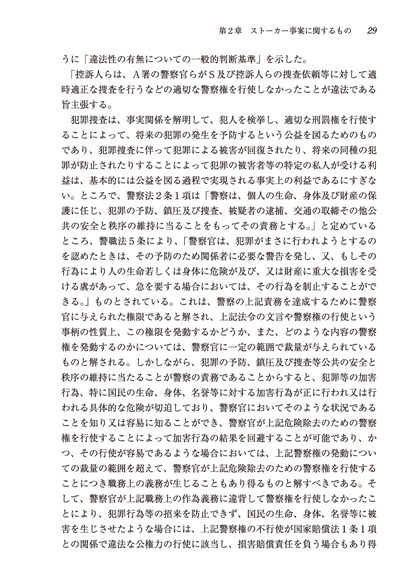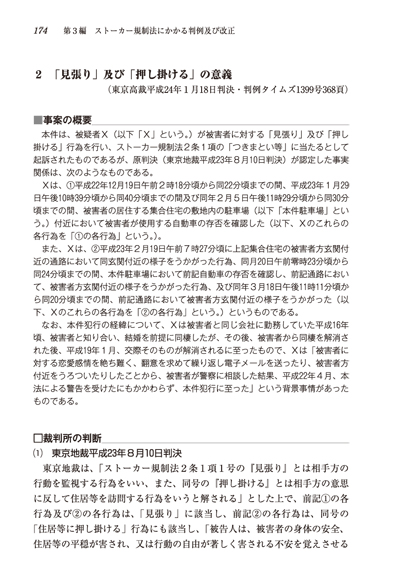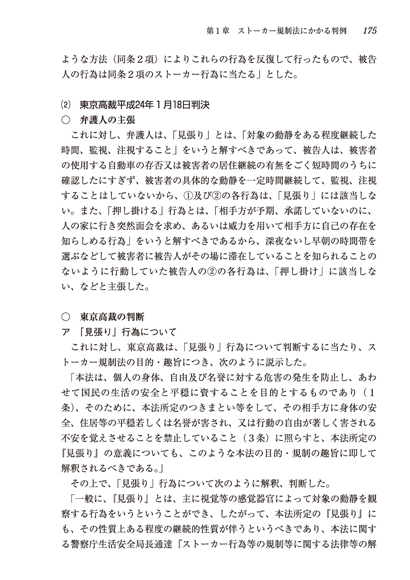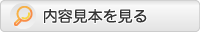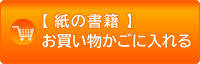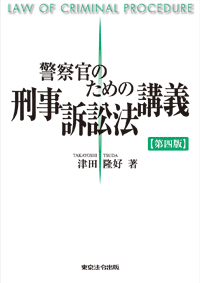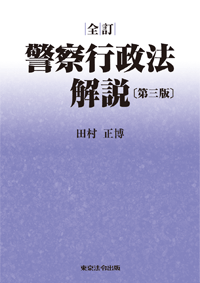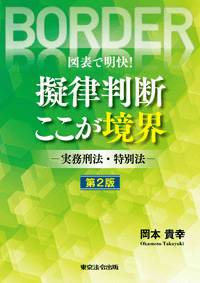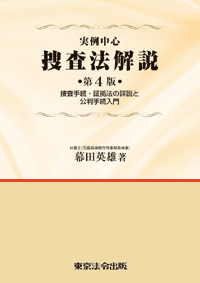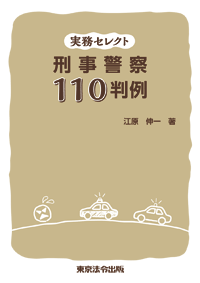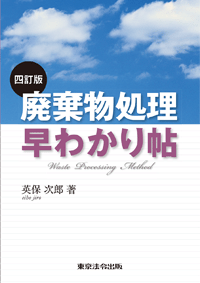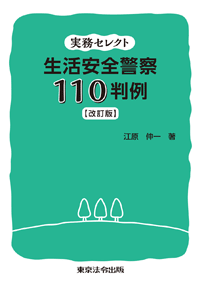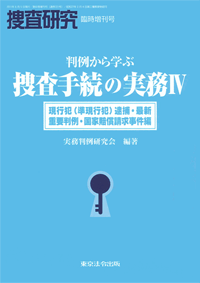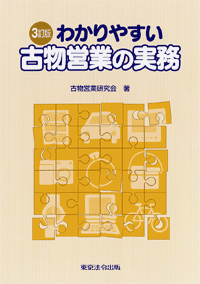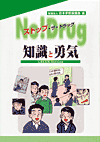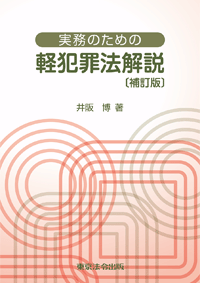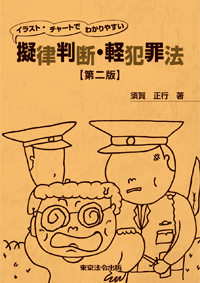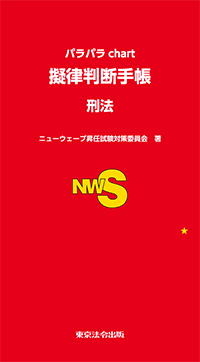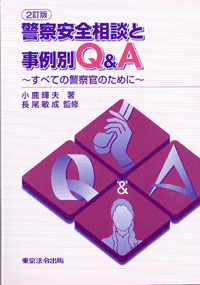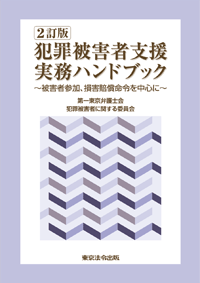国賠判例にみる
権限不行使と警察の責務
〜ストーカー事案等における不作為と判例の立場〜

- 細谷 芳明 著(修士(法学)・元栃木県警察学校長・元警察署長)

- A5判 216ページ

- 1,870 円(消費税込み)

- 1,700 円+税

- ISBN978-4-8090-1410-9
C3032 \1700E
特長
国賠判例に現れたストーカー・初動捜査・警察相談対応事案を追体験的に学べる判例解説書である。
警察権限法の条文上「警察官は・・・・・・することができる。」は、
具体的な危険の切迫 + その予見可能性などがある状況
においては、「・・・・・・しなければならない。」と解釈され、その不作為については賠償責任が生ずることがある。
本書は有名判例の事案の概要(流れ)を詳細に提示し、警察の対応も具体的に示す。結果的に、そのとき警察官(警察組織)はどう動くべきであったかを検討するのに最適な内容とした。
【その他の特長】
- 裁判所の考え方を知ることで、警察活動遂行のポイントを掴む一冊。
- 登載判例は「桶川事件」「太子町ストーカー事件」「石橋事件」「神戸事件」「ナイフ一時保管懈怠事件」。
- 最近のストーカー規制法関連裁判例、法改正要点なども紹介。
はしがき
本書は、ストーカー事案等の対応において、警察権限の不行使が争われた国家賠償請求事件に対する裁判所の考え方(判例法理)を、詳細な事案を踏まえて紹介するものである。
このストーカー事案対応をめぐり、警察権限の不行使が社会の注目を集めた桶川事件につき、さいたま地裁が平成15年2月26日判決において、初めて裁判所の考え方を示した。
警察権限の不行使に関し、さいたま地裁判決が導いた「違法性の有無についての一般的判断基準」(裁量権収縮論に依拠したものと考えられる。)は、その後の類似の国家賠償請求事件(太子町ストーカー事件や神戸事件など)にも影響を与えたといえることから、まず、この判断基準について詳しく検討している。
もっとも、これらの事件は最高裁まで争われたが、最高裁はいずれも上告棄却したため、ストーカー事案や初動捜査活動等における警察権限の不行使についての最高裁の考え方は、必ずしも明確とはいい難いと思われる(薬害や公害訴訟などにおいて、最高裁は裁量権消極的濫用論を採用しているものとみられる。)。
次に、警察権限の不行使が違法と評価された場合、生じた生命・身体に対する重大な結果との間に因果関係の存否が問題とされるが、その判例(最高裁昭和57年1月19日第三小法廷判決)が、本書の冒頭に取り上げたナイフ一時保管懈怠(け たい)事件である。因果関係の問題は、ストーカー事案や初動捜査活動等における警察権限の不行使についても争点とされ、国家賠償請求事件においても不法行為と同様な考え方で因果関係の存否が判断されているため、当該事件の中で裁判所の考え方を解説している。
さらに、生じた生命・身体に対する重大な結果との間に因果関係が認められなかった場合、裁判所は被害者(遺族)救済のために、どのような判例法理を採用しているか(太子町ストーカー事件や石橋事件など)についても掘り下げて解説している。
加えて、ストーカー規制法にかかる重要な判例、最新の同法の改正内容及び平成31年3月29日付け警察庁通達「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への迅速かつ的確な対応の徹底について」(警察庁ウェブサイト参照)のあり方についても補足・言及している。
本書は、各種事案への初動対応に当たっている、主に地域警察官にとって必要不可欠な警察権限の行使のあり方について、問題とされた事案を詳しく紹介し、それに対する裁判所の考え方とその評価等を論じたものである。
本書で取り上げた事案は、警察(学校)教養などで一般的に言及されても、裁判所の本質的な考え方まで語られることが少ないことから、どの事案から読み進めても容易に理解が可能となるよう、重複をいとわず詳しく解説したものである。
上記のような視点から本書を構成したもので、他に類書もないことから、少しでも今後の実務における適切な警察活動に資することができるならば、筆者としても幸甚に思うところである。
最後に、本書を刊行するに当たり、平成22年4月から同28年3月まで、専修大学法学部において各先生から民法(総則、物権法、債権法、不法行為法、民法ゼミ等)、行政法及び行政救済法等のご指導を賜り、さらに同大学院法学研究科において行政法特論、刑事学特論、刑事訴訟法特論及び刑事訴訟法演習等のご指導を賜り、特に刑事訴訟法を専攻した際、指導教授であった滝沢誠先生(現・中央大学法科大学院教授)には、現在も引き続き定期的な判例研究会において熱いご指導を賜り、その学恩に深く感謝申し上げます。
令和2年2月吉日
修士(法学)
細谷 芳明
(元栃木県警察学校長・元警察署長)
目次
- 序 章
- 第1編 警察権限の不行使と国家賠償をめぐる判例の基本的視点
-
- 1 ナイフ一時保管懈怠事件
- 2 桶川事件
- 3 太子町ストーカー事件
- 4 神戸事件
- 5 石橋事件
-
- 第2編 捜査権限不行使と国家賠償
- 第1章 犯罪防止等に関するもの
- ナイフ一時保管懈怠事件
(最高裁昭和57年1月19日第三小法廷判決・民集36巻1号19頁)
- ナイフ一時保管懈怠事件
- 第2章 ストーカー事案に関するもの
- 1 桶川事件
(さいたま地裁平成15年2月26日判決・判例時報1819号85頁) - 2 太子町ストーカー事件
(神戸地裁平成16年2月24日判決・判例時報1959号52頁)
- 1 桶川事件
- 第3章 初動捜査活動(警察相談)に関するもの
- 1 神戸事件
(神戸地裁平成16年12月22日判決・判例時報1893号83頁) - 2 石橋事件
(東京高裁平成19年3月28日判決・判例時報1968号3頁)
- 1 神戸事件
- 第1章 犯罪防止等に関するもの
- 第3編 ストーカー規制法にかかる判例及び改正
- 第1章 ストーカー規制法にかかる判例
- 1 ストーカー行為とは、法2条1項1号から8号までの同一の特定の行為を反復することか、それとも各号の異なる行為を反復した場合でもよいか
(最高裁平成17年11月25日第二小法廷決定・刑集59巻9号1819頁) - 2 「見張り」及び「押し掛ける」の意義
(東京高裁平成24年1月18日判決・判例タイムズ1399号368頁) - 3 「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」及び「反復」に該当するか否かが争点とされた事案
(福岡高裁平成28年7月5日判決・判例タイムズ1431号138頁) - 4 ストーカー規制法の憲法適合性の問題
(最高裁平成15年12月11日第一小法廷判決・刑集57巻11号1147頁)
- 1 ストーカー行為とは、法2条1項1号から8号までの同一の特定の行為を反復することか、それとも各号の異なる行為を反復した場合でもよいか
- 第2章 ストーカー規制法の改正
- 1 改正の意義
- 2 ストーカー規制法の一部改正の主な骨子
- 3 ストーカー規制法の一部改正の内容
- 第1章 ストーカー規制法にかかる判例
- 結びに代えて ―警察活動のあり方―
-
- 1 ストーカー事案の相談等件数
- 2 ストーカー事案をはじめ恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の基本通達
- 3 おわりに
-
おすすめ商品